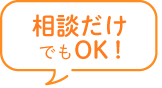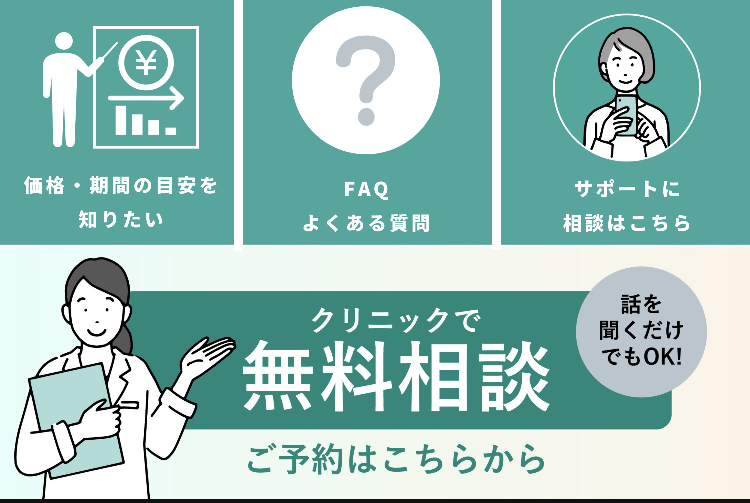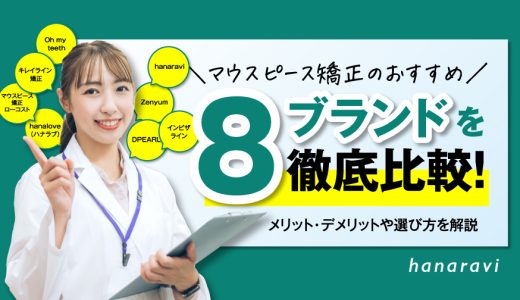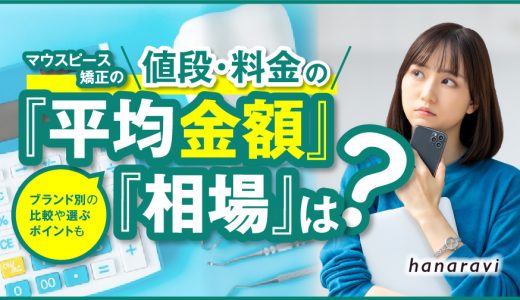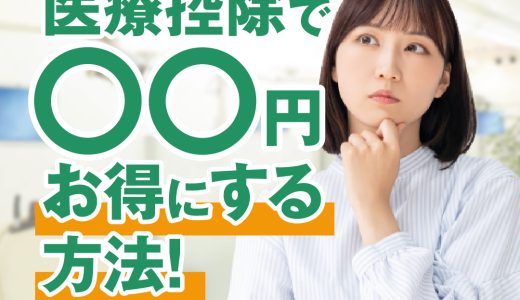下顎が前に出ている「しゃくれ」と呼ばれる状態は、しばしば矯正治療で目にする「受け口(うけぐち)」という歯並びの状態と混同されてがちです。
しかし、しゃくれと受け口は実際にはまったく違う状態を指します。
この記事では、しゃくれとはそもそも何なのか、どのような治療で治せるのかなどを解説します。
自分の歯並びが受け口かもしれない、どれくらいの費用で治療できるのか気になる人は、LINEから簡単に費用の目安がわかります。
無料相談も受け付け中なので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
目次
1. しゃくれは「顎が出ている状態」の総称

「しゃくれ」とは、下顎が前方に出ている、あるいは顎が長く出ているように見える状態を指す一般的な表現です。
医学的な診断名ではなく、輪郭の形状を表す俗語として使われます。
しゃくれの程度は人それぞれです。
軽度であればあまり目立たない場合もありますが、重度になると横顔の印象に大きく影響し、コンプレックスを抱える方もいるでしょう。
(1)遺伝的要因〜骨格的な問題
しゃくれは、遺伝的要因と環境的要因の両方が関係しています。
遺伝的要因の場合、両親のどちらか、あるいは両方がしゃくれの場合、子供もしゃくれになる可能性が高くなります。
遺伝的要因が関係している場合、骨格自体に影響が出ていることが考えられます。
(2)環境的要因〜しゃくれやすい生活習慣
しゃくれは遺伝的な要因だけでなく、幼少期の習慣が原因で発症するケースもあります。
顎の骨の成長はまだ未発達な乳幼児期や成長期において、特定の習慣を続けることによって、将来的に顎の骨格や歯並びに影響を与える可能性があります。
具体的には、以下の生活習慣がある人の場合、顎がしゃくれやすいため注意が必要です。
|
要因 |
具体的な内容 |
|---|---|
|
舌の癖 |
舌を前に突き出す癖がある場合、歯並びに影響が出てしゃくれになることがあります。 |
|
口呼吸 |
口呼吸を続けていると、顎の発達に影響が出てしゃくれになることがあります。 |
|
指しゃぶり |
指しゃぶりを長期間続けていると、歯並びや顎の発達に悪影響を及ぼし、しゃくれになることがあります。 |
|
うつぶせ寝 |
うつぶせ寝は、顎に負担をかけ、発達に影響を与えるため、しゃくれにつながることがあります。 |
|
頬杖 |
頬杖をつく癖も、顎の発達や歯並びに悪影響を与えるため、しゃくれの原因となることがあります。 |
矯正前から矯正後までの歯の動きを動画で確認することができ、具体的な仕上がりイメージを確認したうえで矯正を始められます。
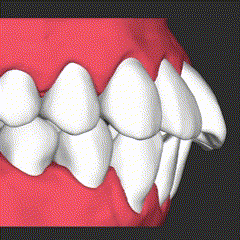
2. しゃくれの種類
しゃくれには、その原因となる骨格や歯並びの状態によっていくつかの種類があります。主な種類は以下の通りです。
(1)下顎前突症(かがくぜんとつしょう)
通常、私たちは口を閉じているとき、上のはが下の歯よりやや前に覆いかぶさるようなかみ合わせとなります。
しかし下顎前突症(かがくぜんとつしょう)の場合、下の前歯が上の前歯よりも前に出たかみ合わせとなり、顎がしゃくれて見えてしまうのです。
下顎前突症は、受け口や反対咬合とも呼ばれます。
単純に歯の噛み合わせだけが反対になっている「歯性」の下顎前突症と、骨格的にで下顎が成長している「骨格性」の下顎前突症の2種類があります。
(2)上顎後退症(じょうがくこうたいしょう)
上顎後退症(じょうがくこうたいしょう)とは、上顎の成長が不足している、もしくは後退している状態です。
その結果、下顎が相対的に前に出ているように見え、しゃくれ顔と認識されることがあります。
下顎前突症(受け口)と似た見た目になるほか、噛み合わせの異常や口呼吸などが挙げられます。
(3)両顎前突症(りょうがくぜんとつしょう)
両顎前突症(りょうがくぜんとつしょう)は上下顎前突症(じょうげがくぜんとつしょう)とも呼びます。
上顎と下顎の両方が前に出ている状態で、上顎前突症と下顎前突症の特徴を併せ持ち、口元全体が突出しているように見えます。
両顎前突症の場合、口を閉じにくかったり、常に口が開いている状態になることがあります。
また、歯並びにも影響が出やすく、上下の前歯が出ていたり、ガタガタに乱れていることもあります。さらに、発音に影響が出る場合もあります。
hanaravi(ハナラビ)が提携している歯科医院は、確かな技術を持つ歯科医師が皆さんの歯並びや顎の状態を丁寧にチェックして、最適な治療方法を提案します!
患者さんひとりひとりにあった、最適な矯正計画を提案します。
3. しゃくれと受け口の違い
しゃくれと受け口は、顎が出ている状態を表す言葉として混同されがちですが、厳密には異なる意味を持ちます。
冒頭で紹介したとおり、「しゃくれ」とは顎が出ている状態全般を指す俗語です。
顎が前方に突出している、あるいは顎が長いことで、横顔から見たときに顎が目立つ状態を「しゃくれ」と表現することが多いです。
そして、「受け口」は不正咬合(歯並びが悪い状態)の一種である下顎前突症を指す言葉であり、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態を指します。
すべての受け口の人はしゃくれ気味に見えますが、しゃくれの人は必ずしも受け口とは限りません。
顎の骨格自体が前に出ている場合や、歯並びは正常でも顎が長い場合なども「しゃくれ」と表現されることがあります。
しゃくれの程度は人それぞれであり、軽度であればほとんど気づかれない場合もあります。
しかし、顎の突出が顕著な場合は、審美的な問題だけでなく、噛み合わせや発音にも影響を及ぼす可能性があります。
4. しゃくれの症状と見た目への影響
しゃくれは日常生活にどのような影響を与えるのでしょうか? 見た目に与える印象や、生活するうえでの不便な点をまとめました。
(1)口元が突出してEラインが乱れてしまう
Eラインとは、鼻の先端と顎の先端を結んだラインのことです。
美しい横顔の基準として用いられ、このライン上に唇が収まっているのが理想的とされています。
しゃくれの場合、下顎や口元が前方へ突き出た見た目となるため、Eラインよりも唇が前に出てしまう傾向があります。
|
しゃくれの程度 |
Eラインとの関係 |
横顔への影響 |
|---|---|---|
|
軽度 |
唇がEラインより少し出ている |
横顔に違和感が出始める |
|
中等度 |
唇がEラインより明らかに出ている |
横顔の印象が大きく変わる |
|
重度 |
唇がEラインよりかなり出ている |
横顔のバランスが崩れ、強い印象を与える |
こうした見た目がコンプレックスとなり、口元を隠すような仕草をしてしまったり、写真撮影を避けるようになったりするケースが少なくありません。
(2)噛み合わせに問題が生じやすい
しゃくれは顎の突出によって、噛み合わせの問題を引き起こしやすいとされています。
しゃくれのように顎の前後関係が通常と異なる場合、上下の歯列が本来の位置で咬み合いません。
下顎が前に出た状態では、奥歯をしっかり噛み合わせる位置を保つのが難しくなります。
結果、一部の歯と歯だけの負担が増えたり、全体的に噛み合わせが浅くなったりするなど、咀嚼機能が低下しやすいです。
(3)発音への悪影響
しゃくれの場合、上下の歯の噛み合わせの位置関係がズレているため、発音に影響が出ることがあります。
発音は舌や歯、唇を使って空気を調整しています。上下の顎の位置関係が適切でないと、発音が難しくなってしまうのです。
具体的には、舌先が上の歯の裏側に付きにくくなるため、サ行やタ行などの発音が不明瞭になりやすい傾向があります。
また、上下の歯の間に隙間があると、空気がもれてしまい、他の音にも影響が出ることがあります。
発音の不明瞭さは、日常生活の中で円滑なコミュニケーションを阻害する可能性があります。
人前で話す機会が多い方や、仕事で正確な発音が求められる方は、しゃくれによる発音への影響を深刻に捉える必要があるでしょう。
(4)顎関節症のリスクも高くなる
下顎が前に出ていると、食事や会話の際に上下の歯が正しく噛み合わず、顎関節や咀嚼筋(そしゃくきん)に負担がかかりやすくなります。
その結果、顎関節症(顎が痛い、音がする、口が開けにくいなど)のリスクが高くなることもあります。
しゃくれは歯科医院などで相談・診断・治療が受けられます。
まずはLINEでの相談や来院しての無料相談などで、どのような治療方法が最適なのかをチェックしてみましょう。
5. しゃくれの治療方法
しゃくれの治療法は、その原因や症状の程度によって異なりますが、主に矯正治療と外科手術の2種類(あるいは両方を組み合わせた治療方法)があります。
(1)矯正治療(歯科矯正)
歯科矯正は、歯の位置を調整することで受け口を改善する主な方法です。
歯の移動を利用した治療方法であり、骨格性のしゃくれには効果が限定的という弱点があります。
すべてのしゃくれを矯正治療で治すことはできないとされる理由がここにあります。
しかし、軽度のしゃくれや歯並びが原因のしゃくれには歯科矯正が非常に有効です。
歯科矯正にはワイヤー矯正、マウスピース矯正などさまざまな方法があり、患者様の歯の状態やライフスタイルに合わせて選択できます。
(2)外科手術
骨格的な問題が大きいしゃくれの場合に有効な治療法です。
主な手術としては下顎骨切り手術があり、下顎の骨を切断して顎の形状を根本的に改善します。
下顎骨切り手術は、一般的に全身麻酔で行います。
一泊程度の入院が必要で、手術後の腫れは1週間程度でひきます。
他にも、分節骨切り術(歯槽骨切り術)やオトガイ形成術といった手術方法があります。
歯科矯正だけでは改善が難しい、重度のしゃくれにも対応可能です。
メリットとしては、骨格レベルでの改善が可能なため、顔貌の劇的な変化が期待できます。
デメリットとしては、外科手術が必要となるため身体への負担が大きいこと、入院が必要となること、費用が高額になることなどが挙げられます。
(3)2つの治療方法の費用相場
矯正治療と外科手術のそれぞれの費用相場は以下の通りです。
|
治療方法 |
費用相場 |
|---|---|
|
矯正治療(歯科矯正) |
60万円~170万円 |
|
外科手術 |
80万円~150万円 |
矯正治療の費用は、使う矯正装置の種類(ワイヤー、マウスピースなど)や素材、矯正範囲(前歯だけか歯全体を動かすのか)などで変化します。
外科手術の場合も、手術の内容によって料金が大きく変化します。
また、いずれの治療方法は自由診療という扱いになるケースが大半ですが、条件が合えば保険適用で治療を受けることができます。
外科手術の場合は、顎関節症などの症状が見られた場合、保険適用が可能です。
歯科矯正はいくつかの条件があります。以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
6. しゃくれを予防・改善するためにできること
しゃくれは遺伝的な要因だけでなく、幼少期の生活習慣も影響します。
改めて、しゃくれにつながる習慣を一覧で確認しましょう。
|
要因 |
具体的な内容 |
|---|---|
|
舌の癖 |
舌を前に突き出す癖がある場合、歯並びに影響が出てしゃくれになることがあります。 |
|
口呼吸 |
口呼吸を続けていると、顎の発達に影響が出てしゃくれになることがあります。 |
|
指しゃぶり |
指しゃぶりを長期間続けていると、歯並びや顎の発達に悪影響を及ぼし、しゃくれになることがあります。 |
|
うつぶせ寝 |
うつぶせ寝は、顎に負担をかけ、発達に影響を与えるため、しゃくれにつながることがあります。 |
|
頬杖 |
頬杖をつく癖も、顎の発達や歯並びに悪影響を与えるため、しゃくれの原因となることがあります。 |
しゃくれの悪化を防ぐには、ここで紹介されている習慣をやめることが重要です。
具体的にどうすればいいのか、簡単にまとめました。
-
舌の癖の改善⋯舌の形を意識的に変える(平らにしたりとがらせたりする)、口の中で舌をさまざまな方向に動かすといったエクササイズを通じて、舌を正しい位置(上顎にくっついた状態)に矯正する
-
口呼吸の改善⋯鼻呼吸を意識的に行う、舌を正しい位置にする、口にテープを貼って寝る(睡眠中に鼻呼吸を促す)
-
指しゃぶりの改善⋯乳幼児期からのトレーニングで指しゃぶりをしないようにする
-
うつぶせ寝の改善⋯あお向け、横向けでの睡眠を習慣づける、自分に合った寝具を使用する
-
頬杖の改善⋯頬杖をつくのは頭を支える首・肩・背中が凝っているケースが多いため、日頃からストレッチなどでこれらの筋肉をほぐす。普段使っている机や椅子が、自分の背丈に合ったものかを確認する
こうした習慣の改善は重要な一方、しゃくれの改善では矯正治療や外科手術といった治療が必須なケースが多いです。
口周りで生活の不便を感じていたり、見た目にコンプレックスを抱いている場合は、なるべく早く近くの歯科医院に相談してみてください。
hanaraviのLINEからも、実績と信頼のある歯科医院へ問い合わせ・無料相談予約が可能です。
7. さまざまな問題を引き起こすしゃくれを治したい人はhanaravi(ハナラビ)へ

「しゃくれ」について、その種類や受け口との違い、治療方法、予防法などを解説しました。
しゃくれと受け口は混同されがちですが、受け口はしゃくれの一種で、下顎が上顎よりも前に出ている状態を指します。
つまり、すべての受け口はしゃくれですが、すべてのしゃくれが受け口というわけではありません。
しゃくれは、横顔のEラインの崩れや口元が出ている印象を与えるだけでなく、噛み合わせの問題や発音への影響など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
しゃくれに困っている人は、まず歯科医院に相談のうえ、どのような治療方法が自分には最適なのかを確かめてみましょう。
信頼できる歯科医院に診療と治療をお願いしたい人は、hanaravi(ハナラビ)へご相談ください。
hanaraviは、医師・各務康貴(かくむやすたか)が幅広い世代の口腔環境をよくしたいという想いから立ち上げられた、マウスピース矯正ブランドです。
hanaraviは患者様一人ひとりに最適な治療を提供できるよう、ワイヤー矯正・マウスピース矯正いずれにも詳しい、厳選された専門の歯科医師とのみ提携しています。
矯正経験が豊富な医師が治療を担当するので、安心して矯正ができます。
また、月々3,600円(税抜)※と非常にリーズナブルな価格で歯科矯正を受けられます(※Basicプラン年利2.5%で91回払いの場合)。
公式LINEアカウントから症状別の費用目安がチェックできますので、まずはお気軽にご確認ください。